1969年7月のアトランタ・ポップ・フェスティバルにおいて12万人の前でパワフルなライヴ・パフォーマンスを見せて話題騒然。その話題が冷めやらぬ間の10月にファースト・アルバムを発表し、ハード・ロックの新人としては全米27位という好成績を残します。彼らのマネージャーでありプロデューサーでもあったテリー・ナイトのバンド(ザ・パック)のメンバーだったマーク・ファナーとドン・ブリューワーが紆余曲折(この間にクレイグ・フロストとバンドを組んでいる)の後、メル・サッチャーを加え68年も終わろうとする時期にスリーピース・バンドとして新たにスタートしたのが、グランド・ファンク・レイルロードなのです。バンドとしてのメジャー契約は69年5月にキャピトル・レコードと交わされました。69年10月18日、彼らの本拠地のデトロイトで行われたツェッペリンのコンサートのオープニング・アクトで完全にツェッペリンを喰ったという伝説が彼らの人気に拍車をかけます。
ライブの反応やアルバムのランキングなどの高評価によりキャピトルサイドもプロモーションを積極的に懸け、続けざまにアルバムを発表していきます。早くも69年の暮れにはセカンドを発表し全米11位という好成績を収め、70年7月に発表したサード・アルバムでは遂に一桁台の堂々の6位を獲得、同11月に発表したライヴ・アルバムでは5位と快進撃は続いていきます。翌71年にも『Survival』を4月に、『E Pluribus Funk』を11月に発表し、それぞれ6位と5位にランキングさせます。ほとんどの楽曲を手掛けるマーク・ファナーのコンポーザーとしての力量が十二分に発揮されているのはもちろんですが、さぞかし忙しかったのではないかと思います。しかし、育ての親ともいえるテリー・ナイトとの間に金銭的なトラブルが発生し訴訟問題に発展、蜜月の日々に終わりがやってきます。双方が損害賠償を求めての泥沼の訴訟合戦の末、メンバー側が負けた形になるのです。
独立独歩の道を歩むこととなった彼らは、キャピトルと再契約をします。旧知のキーボーディストのクレイグ・フロストに協力を仰ぎ72年9月に『PHOENIX』を発表、全米7位に食い込みます。その後、フロストを正式にメンバーに加え『We're an American Band』を発表、全米2位(シングルのタイトル曲は見事1位)を獲得し不動の地位を築きます。74年発表の『Shinin' On』、『All the Girls in the World Beware!!!』をベスト10に送り込みますが、ポップさを増した彼らにも終焉の時がやってきます。キャッチーなメロディで時代の波に乗った彼らでしたが、ハード・ロックの衰退とともによりポップ性を追求した作品はファンに受け入れてもらえず、76年に解散します。81年に再結成(メルは不参加)しますが、83年にふたたび解散しています。97年にオリジナルメンバーで再々結成されますが、現在はマークが離れ独自のバンドで活動中です。
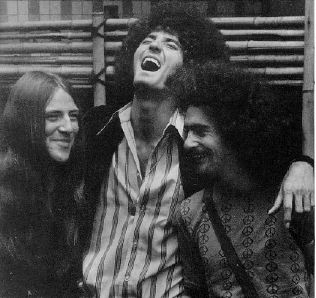
左より
MARK FARNER (G,V)
DON BREWER (Dr,V)
MEL SCHACHER(B)
(1969)
(1969)
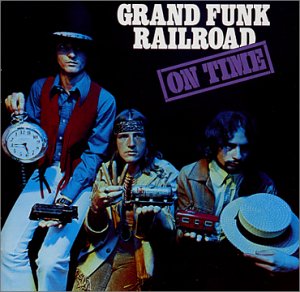 「アー・ユー・レディ」、「タイム・マシーン」、「ハートブーカー」などGFRといえばという彼らの代表曲でありライヴの定番を含む傑作デビュー・アルバムです。ブルーズ、R&B色が強く出たアメリカン・ハード・ロックの基本形とも呼べるスタイルは、演奏はまだまだ荒削りなところがありますが、キャッチーなメロディを背負って3Dのようにガンガン迫ってくるのです。
「アー・ユー・レディ」、「タイム・マシーン」、「ハートブーカー」などGFRといえばという彼らの代表曲でありライヴの定番を含む傑作デビュー・アルバムです。ブルーズ、R&B色が強く出たアメリカン・ハード・ロックの基本形とも呼べるスタイルは、演奏はまだまだ荒削りなところがありますが、キャッチーなメロディを背負って3Dのようにガンガン迫ってくるのです。
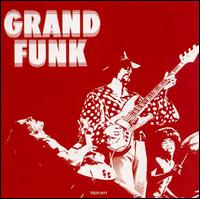 前作同様にブルースを基調にしたパワフルな作品群です。キャッチーなメロディも健在ですが、長尺の作品が4曲含まれておりシングルよりもアルバム重視の姿勢が見て取れます。8分近い曲が2曲、アニマルズのカヴァー「孤独の叫び」にいたっては9分半もの大作なのです。テクニックで迫れない分、爆走列車のごとく暴力的でスリリングなのです。
前作同様にブルースを基調にしたパワフルな作品群です。キャッチーなメロディも健在ですが、長尺の作品が4曲含まれておりシングルよりもアルバム重視の姿勢が見て取れます。8分近い曲が2曲、アニマルズのカヴァー「孤独の叫び」にいたっては9分半もの大作なのです。テクニックで迫れない分、爆走列車のごとく暴力的でスリリングなのです。
(1970)
(1971)
(1971)
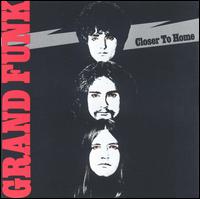 ヘヴィなリフが炸裂するオープニングなどブリティッシュ・ハード・ロックへの挑戦とも言えるようなハード・ロック色を濃くした作品です。前作の大作志向は、ついに10分にも及ぶ組曲「I'm Your Captain (Closer to Home)」への挑戦という形で実を結びます。音だけでなくこういうスタイルへのこだわりがブリティッシュ・ロックへの傾倒のように感じられて興味深いのです。
ヘヴィなリフが炸裂するオープニングなどブリティッシュ・ハード・ロックへの挑戦とも言えるようなハード・ロック色を濃くした作品です。前作の大作志向は、ついに10分にも及ぶ組曲「I'm Your Captain (Closer to Home)」への挑戦という形で実を結びます。音だけでなくこういうスタイルへのこだわりがブリティッシュ・ロックへの傾倒のように感じられて興味深いのです。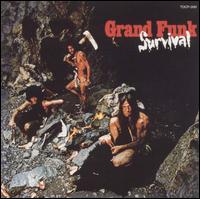 前作のブリティッシュ傾倒から原点回帰してブルース、R&Bなどアメリカンを感じさせるルーズさが貫禄すら感じさせるどっしりした作品です。その落ち着きさゆえか他の作品に比べると地味な印象が否めませんが、じっくりと聴き込むことのできる曲が多く含まれる渋い作品と評価すれば、また違った良さが見えてくるのです。
前作のブリティッシュ傾倒から原点回帰してブルース、R&Bなどアメリカンを感じさせるルーズさが貫禄すら感じさせるどっしりした作品です。その落ち着きさゆえか他の作品に比べると地味な印象が否めませんが、じっくりと聴き込むことのできる曲が多く含まれる渋い作品と評価すれば、また違った良さが見えてくるのです。
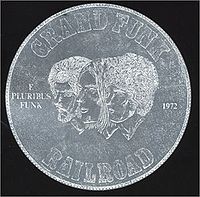 コインを模した変形ジャケットが斬新で話題になった作品です。が、中身の楽曲もなかなか凝った作りになっていて、ゴスペル調のオープニングとシンフォニーを導入した意欲作のラスト曲にハードでスリリングな作品が5曲サンドイッチになっている(もちろんCDでのこと)という構成がドラマチックですらあります。
コインを模した変形ジャケットが斬新で話題になった作品です。が、中身の楽曲もなかなか凝った作りになっていて、ゴスペル調のオープニングとシンフォニーを導入した意欲作のラスト曲にハードでスリリングな作品が5曲サンドイッチになっている(もちろんCDでのこと)という構成がドラマチックですらあります。
(1972)
(1973)
(1974)
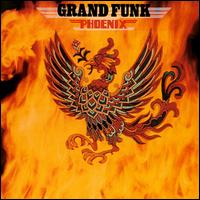 テリー・ナイトと袂を分かちセルフ・プロデュースで創り上げた作品です。本作には旧知のクレイグ・フロストがキーボーディストとして参加しています。それに加えてフィドルのダグ・カーショウが参加、オープニングからそれらをフィーチャーしたインスト曲なのには驚きましたが、アンサンブル重視の姿勢は音の広がりと重厚さをもたらし、隠れ名盤ともいえる作品に仕上がっています。
テリー・ナイトと袂を分かちセルフ・プロデュースで創り上げた作品です。本作には旧知のクレイグ・フロストがキーボーディストとして参加しています。それに加えてフィドルのダグ・カーショウが参加、オープニングからそれらをフィーチャーしたインスト曲なのには驚きましたが、アンサンブル重視の姿勢は音の広がりと重厚さをもたらし、隠れ名盤ともいえる作品に仕上がっています。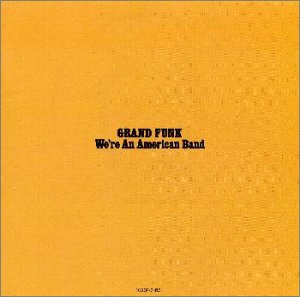 奇才トッド・ラングレンをプロデューサーに迎えて創られた作品は、彼らにロック・ファンのみならず一般大衆にも名前が知れ渡るきっかけを作りました。ハードでありながらキャッチーなメロディと洗練された音は、一級品のレッテルを張るに充分です。ただ、タイトル曲のみが独り歩きし、ハード・ポップなシングルヒットを狙うバンドとして認識される結果を生み出したのは残念です。
奇才トッド・ラングレンをプロデューサーに迎えて創られた作品は、彼らにロック・ファンのみならず一般大衆にも名前が知れ渡るきっかけを作りました。ハードでありながらキャッチーなメロディと洗練された音は、一級品のレッテルを張るに充分です。ただ、タイトル曲のみが独り歩きし、ハード・ポップなシングルヒットを狙うバンドとして認識される結果を生み出したのは残念です。
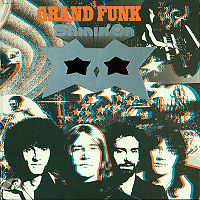 なんと、今となっては恥ずかしいような感じもする赤・青メガネ付きの3Dジャケットです。しかし、当時は業界初という画期的なもの、プロデューサーも前作同様にトッド・ラングレン、前作よりもまとまりのある作品に仕上がっていますが、往年の激しさを知る人間にとっては少し物足りなさすら感じてしまいます。余裕ともいえるような落ち着きが感じられ名実ともにトップ・バンドになったのねぇ。
なんと、今となっては恥ずかしいような感じもする赤・青メガネ付きの3Dジャケットです。しかし、当時は業界初という画期的なもの、プロデューサーも前作同様にトッド・ラングレン、前作よりもまとまりのある作品に仕上がっていますが、往年の激しさを知る人間にとっては少し物足りなさすら感じてしまいます。余裕ともいえるような落ち着きが感じられ名実ともにトップ・バンドになったのねぇ。
(1974)
(1976)
(1976)
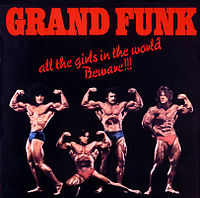 なんと、ラズベリーズやスリー・ドッグ・ナイトで有名なポップ畑のプロデューサーであるジミー・イエナーを迎えての作品です。さらにポップ色を濃くする意図をもって製作されたことは理解できますが、上品で美しい仕上がりは往年のファンにとっては悲しさが先に立ってしまいます。が、2曲もビックヒットが生まれました。ついにポップ・バンドになってしまったのか。
なんと、ラズベリーズやスリー・ドッグ・ナイトで有名なポップ畑のプロデューサーであるジミー・イエナーを迎えての作品です。さらにポップ色を濃くする意図をもって製作されたことは理解できますが、上品で美しい仕上がりは往年のファンにとっては悲しさが先に立ってしまいます。が、2曲もビックヒットが生まれました。ついにポップ・バンドになってしまったのか。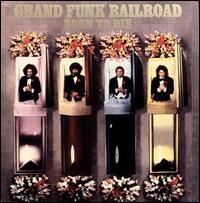 前作同様にジミー・イエナーがプロデュース。タイトルとジャケットのデザインがいけなかったのか、はたまた過去の栄光にすがるような邦題『驚異の暴走列車』がいけなかったのか、ファンの望む方向性とバンドのそれとが大きく食い違っていたのは確かでした。作品としては出来は悪くなく佳曲ぞろいなのですが、いかんせん渋過ぎるのがヒットしなかった理由かも。
前作同様にジミー・イエナーがプロデュース。タイトルとジャケットのデザインがいけなかったのか、はたまた過去の栄光にすがるような邦題『驚異の暴走列車』がいけなかったのか、ファンの望む方向性とバンドのそれとが大きく食い違っていたのは確かでした。作品としては出来は悪くなく佳曲ぞろいなのですが、いかんせん渋過ぎるのがヒットしなかった理由かも。
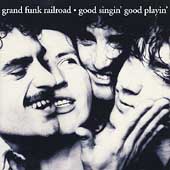 今回は、あのフランク・ザッパがプロデュース。ザッパは、曲によりギターでも参加しており精神錯乱状態をバンドにもたらしていますが、悪い影響を与えているのではなく、GFRに無い部分を補って余りある活躍ぶりです。それは、プロデュースにも言えており、曲間が無い構成は、よりパワフルな感動すら与えてくれます。隠れ名盤の一種といえる作品です。
今回は、あのフランク・ザッパがプロデュース。ザッパは、曲によりギターでも参加しており精神錯乱状態をバンドにもたらしていますが、悪い影響を与えているのではなく、GFRに無い部分を補って余りある活躍ぶりです。それは、プロデュースにも言えており、曲間が無い構成は、よりパワフルな感動すら与えてくれます。隠れ名盤の一種といえる作品です。
(1981)
(1983)
(1970)
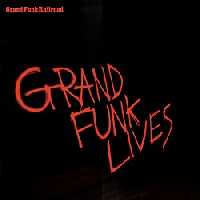 残念ながらメル・サッチャーは参加していませんが、再結成の第一弾、ライヴではなくスタジオ録音作で、リヴズ(生きている)の意味です。マーク・ファナーが主導権を握りスリー・ピースというデビュー当時のスタイルでの作品は、80年代の流れも吸収した音作りがなされ好感が持てます。パワフルなギター・リフなどファンとしては涙ものではないでしょうか?
残念ながらメル・サッチャーは参加していませんが、再結成の第一弾、ライヴではなくスタジオ録音作で、リヴズ(生きている)の意味です。マーク・ファナーが主導権を握りスリー・ピースというデビュー当時のスタイルでの作品は、80年代の流れも吸収した音作りがなされ好感が持てます。パワフルなギター・リフなどファンとしては涙ものではないでしょうか?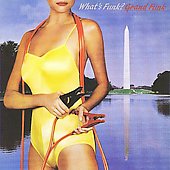 再結成の第2弾です。今回はキーボードを加えての音作りがなされていて、ハードだった前作とは違い妙にまとまりがある作品になってしまいました。個人的には、オープニングの「Rock & Rollamericanstyle」というタイトルに「We're an American Band」の二匹目のドジョウを目指したセンスの良いタイトルが気に入りました。夢よもう一度という彼らの願いがひしひしと感じられます。
再結成の第2弾です。今回はキーボードを加えての音作りがなされていて、ハードだった前作とは違い妙にまとまりがある作品になってしまいました。個人的には、オープニングの「Rock & Rollamericanstyle」というタイトルに「We're an American Band」の二匹目のドジョウを目指したセンスの良いタイトルが気に入りました。夢よもう一度という彼らの願いがひしひしと感じられます。
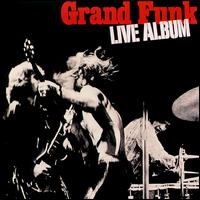 ライヴ・バンドとしての人気絶頂期に発売されただけあって迫力満点の名ライブ盤なのです。ジャケットの印象そのままのパワフルで迫力満点の轟音がガンガン迫ってきます。テクニックなんて関係ない、ロックはパワーだとでも言わんばかりの演奏を2枚組で初めて聴き終えた時には、本当に疲れてしまいました。と同時にえも言われぬ虚脱感というか満足感に襲われるのです。
ライヴ・バンドとしての人気絶頂期に発売されただけあって迫力満点の名ライブ盤なのです。ジャケットの印象そのままのパワフルで迫力満点の轟音がガンガン迫ってきます。テクニックなんて関係ない、ロックはパワーだとでも言わんばかりの演奏を2枚組で初めて聴き終えた時には、本当に疲れてしまいました。と同時にえも言われぬ虚脱感というか満足感に襲われるのです。
(1975)
(1997)
(2002)
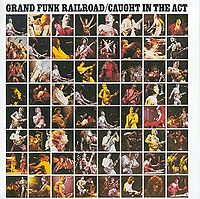 第2期全盛時代の総括ともいえるライブ作品です。録音状態も良く初期のライヴ作品にも劣らない出来栄えです。力で押しまくる初期のライヴ作品とは違い円熟味(それほど歳ではありませんが)を増した演奏は聴き応え十分です。プロデューサーがジミー・イエナーであることも美しさに拍車がかかった原因かもしれません。この作品からGFRに戻っていますので権利が復帰したのでしょう。
第2期全盛時代の総括ともいえるライブ作品です。録音状態も良く初期のライヴ作品にも劣らない出来栄えです。力で押しまくる初期のライヴ作品とは違い円熟味(それほど歳ではありませんが)を増した演奏は聴き応え十分です。プロデューサーがジミー・イエナーであることも美しさに拍車がかかった原因かもしれません。この作品からGFRに戻っていますので権利が復帰したのでしょう。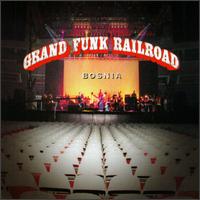 タイトル通りボスニアでのライヴ、ではありません。紛争まっただ中のボスニアを応援する目的で催されたライヴなのです。前年に再々結成したGFR、オーケストラとの共演やピーター・フランプトンとの共演など話題性は十分です。ファンにとっては、「Loneliness」のライヴは貴重なのではないでしょうか。スタジオ作品ではなくライヴで勝負というところにGFRらしさが。
タイトル通りボスニアでのライヴ、ではありません。紛争まっただ中のボスニアを応援する目的で催されたライヴなのです。前年に再々結成したGFR、オーケストラとの共演やピーター・フランプトンとの共演など話題性は十分です。ファンにとっては、「Loneliness」のライヴは貴重なのではないでしょうか。スタジオ作品ではなくライヴで勝負というところにGFRらしさが。
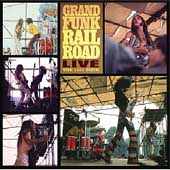 1971年のツアーのから、シカゴ、ニューヨーク、デトロイトの3ヶ所で録られた音源をまとめたものです。しかも、ニューヨークのシェイスタジアムでのコンサートは、チケット発売後わずか24時間でソールドアウトという記録まで打ち立てた凄さが当時のライヴ・バンドとしての彼らの魅力を物語っています。しかし、なぜ2002年になっていきなり発売だったのか。
1971年のツアーのから、シカゴ、ニューヨーク、デトロイトの3ヶ所で録られた音源をまとめたものです。しかも、ニューヨークのシェイスタジアムでのコンサートは、チケット発売後わずか24時間でソールドアウトという記録まで打ち立てた凄さが当時のライヴ・バンドとしての彼らの魅力を物語っています。しかし、なぜ2002年になっていきなり発売だったのか。