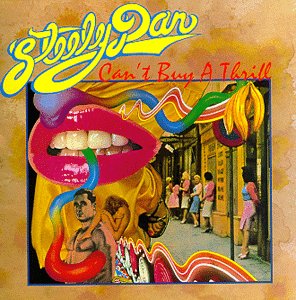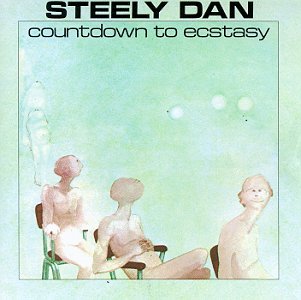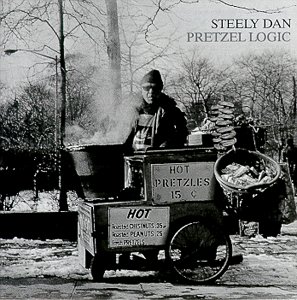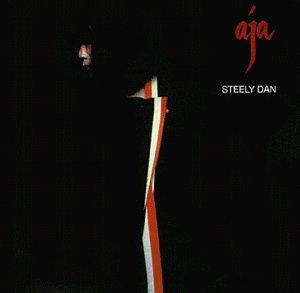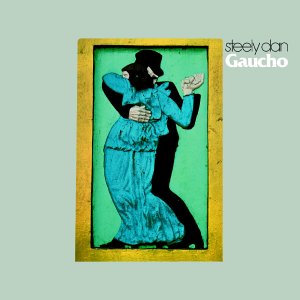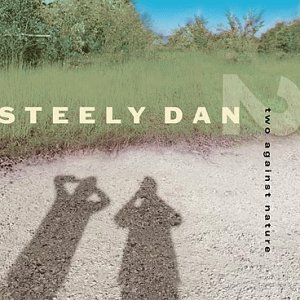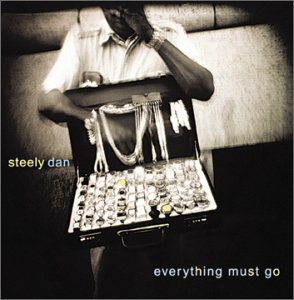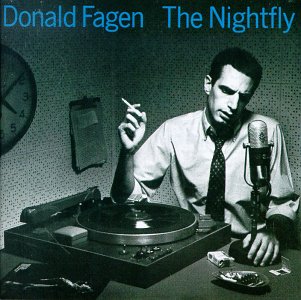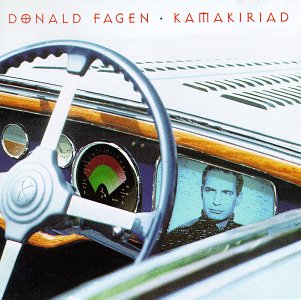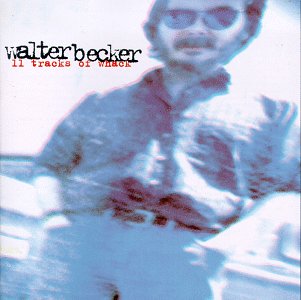STEELY DAN
CAN'T BUY A THRILL(1972) |
STEELY DAN
COUNTDOWN TO ECSTACY(1973) |
STEELY DAN
PRETZEL LOGIC(1974) |
STEELY DAN
KATY LIED(1975) |
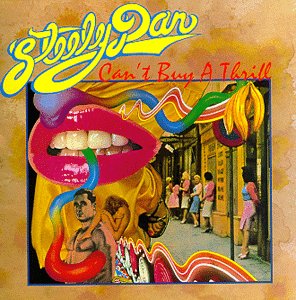
ロックが南部の音楽を吸収する中で、異端とも思えるほどの方向性を示した傑作アルバム。ジェフ・スカンク・バクスター、デニー・ディアスの二枚看板のギタリストを前面に押し出し、ラテン、ジャズなどのリズムを巧みに取り込んだ曲は爽やかで新鮮でした。唯一納得のいかないのは、かなりインパクトのあるタイトルとカヴァー・アートかな。でもこれもセンスの表れかも。
|
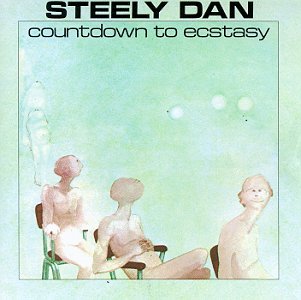
一聴するとロックン・ロール、しかしブルースやジャズが混在しギターワークも楽しい不思議な魅力に溢れた名曲「菩薩」で始まる傑作(ほとんどの作品を傑作だと思っています)アルバム。今回は、ラテン、ジャズのみならずカントリー・テイストも加味された楽しさ溢れる作品に仕上がってます。スタジオミュージシャン15人を適材適所に配置して完璧を求めています。 |
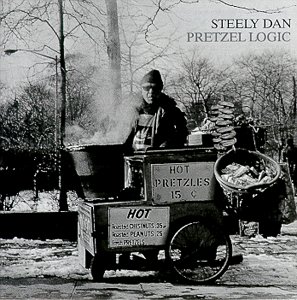
バンドの形態はとっているものの、多数のゲストを迎えて作られた3作目。大胆なホーン・セクションやストリングスの導入の目立つ曲や音の方もギターを筆頭にややヘヴィーになっています。全米4位を獲得した「リキの電話番号」など、これまでの延長線上にある曲もさらにスマートになっています。アメリカでは最高位8位、日本でも人気を定着させたアルバムです。
|

完全にライヴ活動を停止した後に作成された作品です。前作で、ジェフ・バクスターが脱退しドゥービー・ブラザースへ、代わりにジャズ畑よりラリー・カールトンが参加。しかし、ジャズ的なアプローチの曲ばかりではなくブルージーな曲(といってもスティーリー・ダン的解釈の)、ロックン・ロール、サルサ風とバラエティに富んだ構成とゲストの起用方法はさすがです。 |
STEELY DAN
THE ROYAL SCAM(1976) |
STEELY DAN
AJA(1977) |
STEELY DAN
GAUCHO(1980) |
STEELY DAN
TWO AGAINST NATURE(1977) |

デニー・ディアス、マイケル・マクドナルドの記載はあるもののフェイゲン、ベッカーのユニットとしての色彩が濃い作品です。間奏などのギターが前面に出ているせいか、全体的にシャープな印象を受けます。私は、スティーリー・ダンのサウンドが完成した記念すべき一枚だと思っています。できれば、ギターをジェフ・バクスターに弾いてほしかった。文句無しに大傑作です。 |
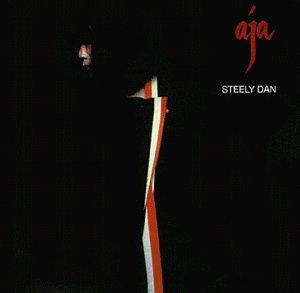
時は、AORやフージョンが大流行。この作品にもその手の大物が多数参加。とはいうものの、そこはフェイゲン、ベッカー、そんじょそこらの人間とは質が違う。大物を歯車のように使い切ってしまった。ドラムなどは7曲に6人も起用する徹底ぶりで、微妙なタッチの違いが楽しめるのも、このアルバムの楽しみ方かもしれません。前作よりは、ジャズ色が強くなった作品です。 |
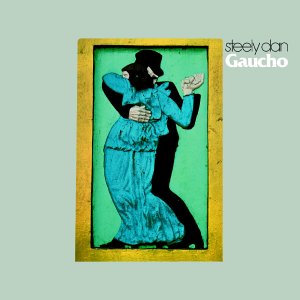
控えめな演奏をバックに上手いとはいえないヴォーカル、それに絡む女性コーラス、そして出来上がったのがセンス溢れる究極の切れ味の曲「バビロン・シスターズ」。前作で頂点に達したかに思われたのは大きな間違い、フェイゲン=ベッカーはまだまだ進化してしまった。よりクールに、より美しく。2曲目などは、単純にして複雑。スティーリー・ダンの凄さが堪能できます。 |
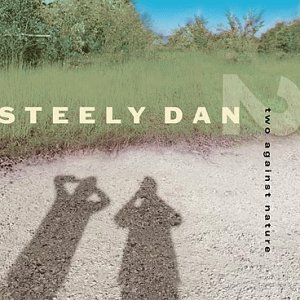
ジ・エンドかと思われたユニットの復活第一弾。期待が大きかったせいもありましたが、残念なできになっていると思います。一定の水準は保ってはいるものの本来のスリリングな部分が少なく、メリハリにかけるような感じです。やはり、二人とも年のせいで丸くなったのでしょうか?しかし、いつも通りバックには、今が旬の凄腕が集まっており高水準の演奏を楽しめることは間違いありません。 |
STEELY DAN
EVERYTHING MUST GO(19) |
DONALD FAGEN
THE NIGHTFLY(1982) |
DONALD FAGEN
KAMAKIRIAD(1993) |
WALTER BECKER>br>11 TRACKS OF WHACK(2000) |
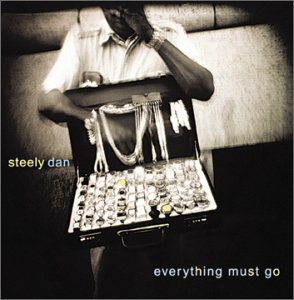
前作発表から3年後の発表された作品。その間ライヴ活動なども行い、ノリの良い内容になっています。さすがに緻密さという点では絶頂期には及びませんが、スティーリー・ダンとしての表現方法が変わったと思えば何ら気になる事はありません。 |
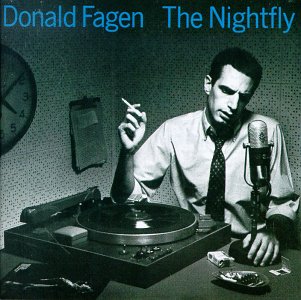
1950,60年代のアメリカを舞台にしたコンセプトアルバムです。詩の内容(都市と郊外の生活:ちょっと暗い)とは裏腹に、かなり切れ味鋭く明るい曲調です。プロデューサーとエンジニアが昔ながらのゲイリー・カッツ、ロジャー・ニコルズだというのも、これまでのスティーリー・ダンとの違和感のなさを演出するには十分すぎる布陣なのではないでしょうか。 |
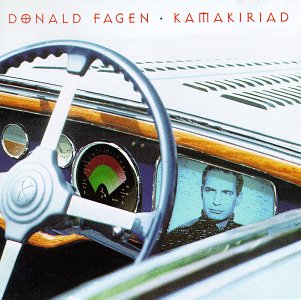
なんと、ウォルター・ベッカーがプロデュース。全盛期のスティーリー・ダンの復活かと思いきや、鋭さがなくなりやわらかい感じに仕上がっています。曲調自体は変わっていませんので、こんなスティーリー・ダンもいいかな、という感じです。だって、ずいぶん年月経ってますから、これでいいのではないでしょうか。聴くほうも歳とってるから、耳に心地よい響きです。 |
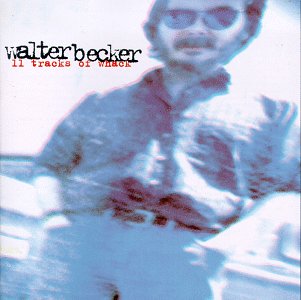
このベッカーのアルバムを聴いて素直に思ったことは、フェイゲンのほうがストレートでベッカーのほうが良くも悪しくもひねくれていたんだなと初めて気づきました。ある意味、スティーリー・ダンはベッカーだったんだと。リード・ヴォーカルを聴いたのも初めてですが、スティーリー・ダンの魂はベッカーだった?。 |